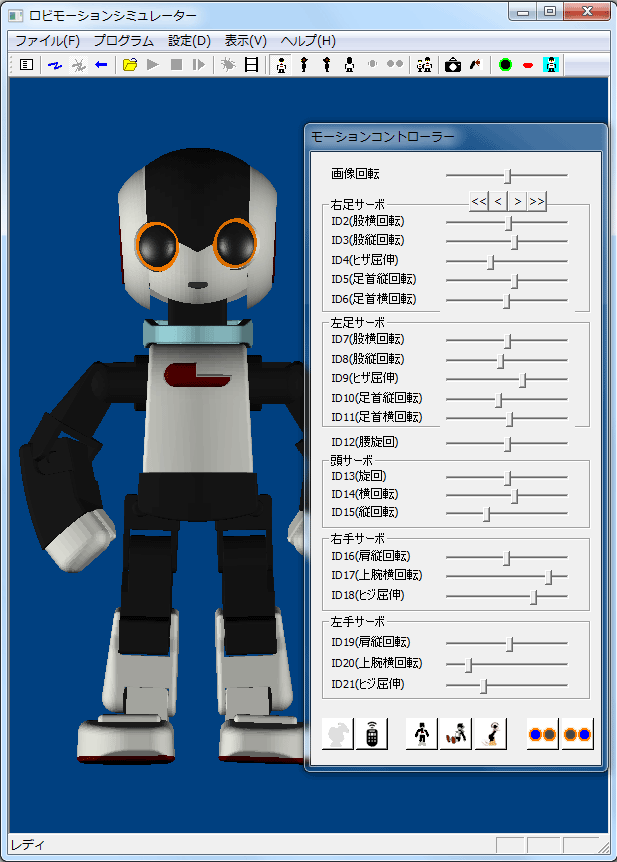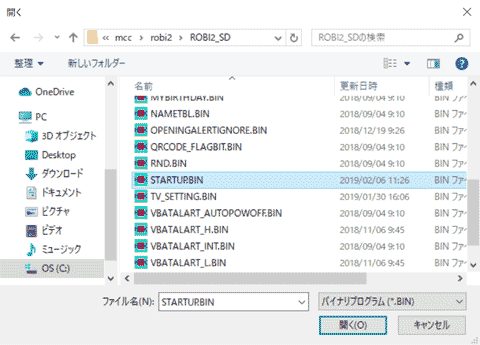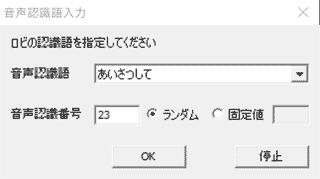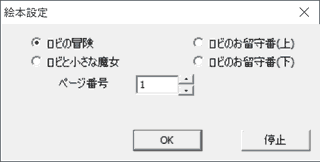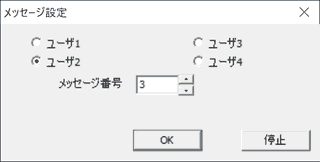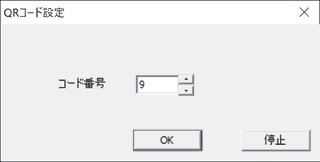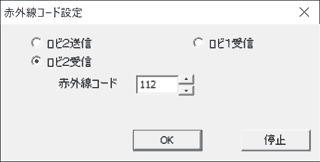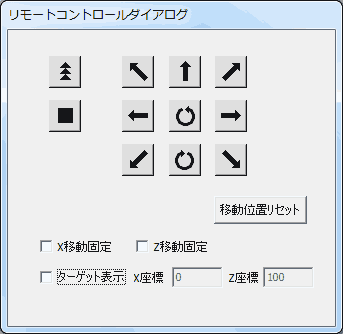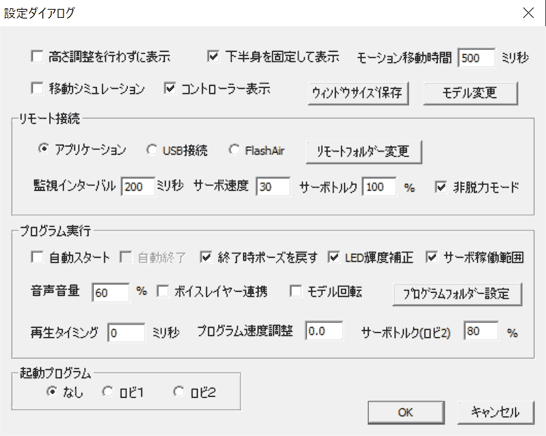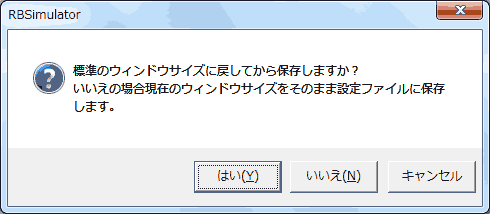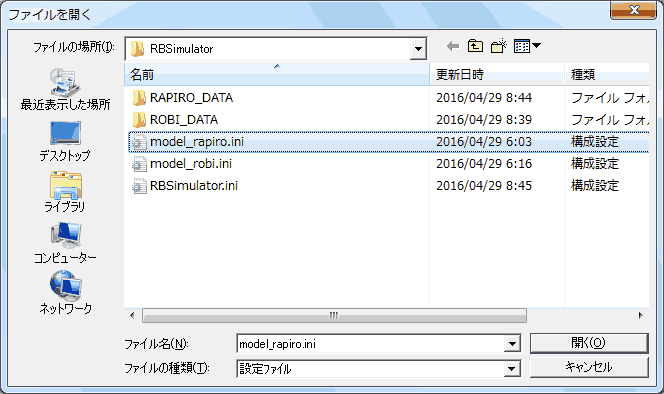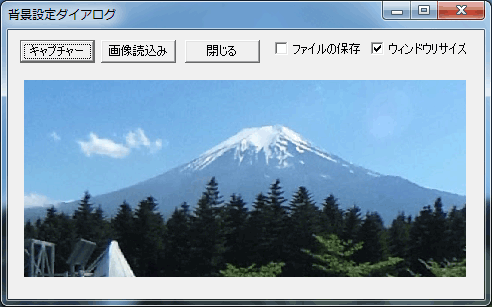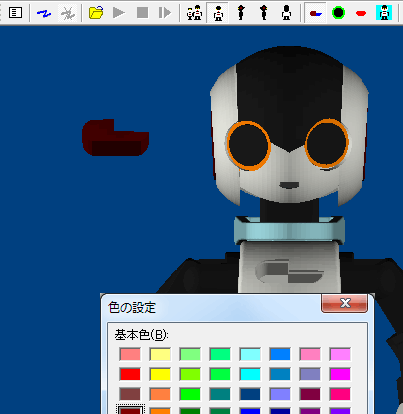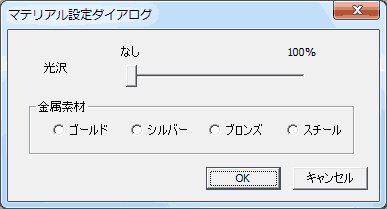ロビモーションシミュレーター
ロビモーションシミュレーターはロビの動きをシミュレーションするWindowsアプリケーションです。
ロビモーションシミュレーターはDirectXを使ってロビを3Dで表示します。
原点や稼働領域の設定はロビと同じにしていますのでロビのデータがそのまま使う事ができます。
ロビのプログラムをロビ標準のものをそのまま動かす事ができます。
プログラムは途中で止めたり1ポーズづつ動かす事もできます。
ロビモーションシミュレーターはロビモーションエディターと連携してモーションエディターで作成したモーションを再生する事ができます。
またUSBやFlashAirでPCに接続した実物のロビに対してポーズを送信したりロビのポーズをキャプチャーする事もできます。
ロビボイスコンバーターと連携すれば音声認識によりシミュレーション画像を操作する事もできます。
3D画像のデータとしてロビの他にいろいろなモデルを用意しています。
免責事項
本アプリケーションを使用することによって、発生した損失や損害に対して株式会社メディアクラフトは一切責任を負いません。
シミュレーション画像の動きはコンピューターの性能に左右されますので低スペックのコンピューターではシミュレーション画像がスムースに動かない場合があります。
またリモート接続でロビを動かす場合はサーボに無理な負荷がかかるとサーボが壊れる事があるので十分注意してください。
インストール
ロビモーションシミュレーターをダウンロードして解凍した中味(RBSimulator.exe(実行プログラム),RBSimulator.ini(設定ファイル),model_robi.ini(ロビのパーツ情報データ),ROBI_DATA(ロビの3Dデータ),D3DX9_37.dll(DirectXランタイムライブラリィ)をWindows PCの適当なフォルダーに置いてください。
本プログラムの設定を変更する場合はファイルの書き変え可能なフォルダーに置いてください。
プログラムの実行
RBSimulator.exeをクリックすると実行できます。
RBSimulator.exeの引数にプログラム名を指定する起動時にそのプログラムを読込み実行可能状態になります。
自動スタートの設定をしておけば起動した後、自動的にプログラムを開始します。
また.RM4ファイルを本プログラムに関連付ければ.RM4ファイルをダブルクリック(開く)するとそのRM4ファイルを開いたり実行する事ができます。
Windows8またはWindows10でインターネットからダウンロードしたプログラムを実行しようとすると「WindowsによってPCが保護されました」というダイアログが表示される事があります。
その場合はこちらの方法で実行する事ができます。
プログラムファイルの関連付け
リモート接続
デバッグ機能
モーションプログラムの作成
背景の制御
ロビモーションランナー
手動操作
ロビモーションシミュレーターを起動すると下記の画面が表示されます。
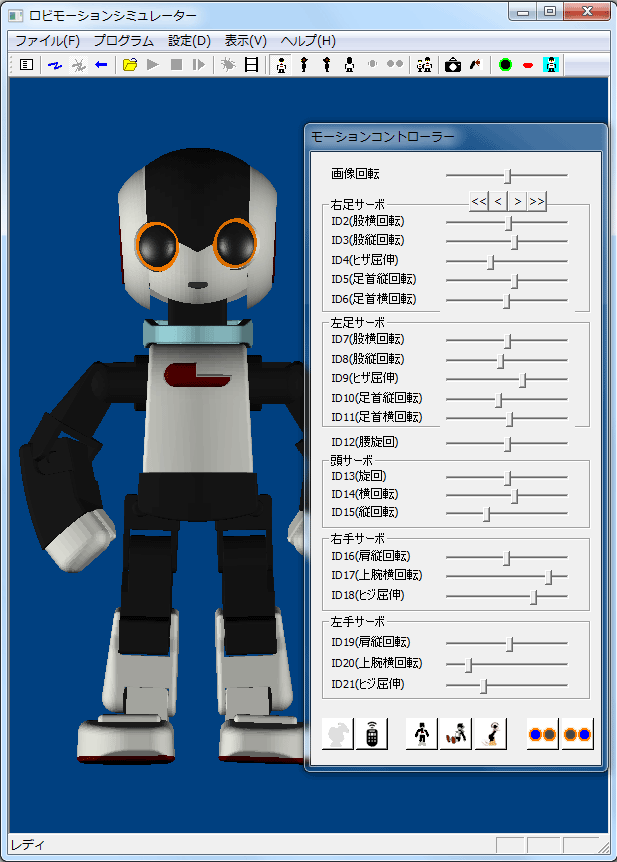
この時、3Dデータを読込むのに時間がかかるので少し時間がかかります。
右にコントロールダイアログが表示されるのでスライダーを左右に動かしてロビのサーボを回転させてロビを動かす事ができます。
サーボは稼働範囲を越えないように設定されていますので左右の稼働範囲が異なる場合、少ない方は稼働範囲を越えてスライダーを動かしてもサーボは可動範囲内で止まります。
一番上のスライダーは画像全体を360°回転させる事ができます。
なおモーションエディターと連携中は手動でサーボを動かせないようにサーボのスライダーは表示されません。
連続再生中でも一番上のスライダーは操作する事ができます。
サーボ原点ボタンはサーボの位置を原点に戻してロビの姿勢を原点ポーズにします。
微調整ボタン は最後に操作したスライダーに対してボタン操作で微調整ができます。
は最後に操作したスライダーに対してボタン操作で微調整ができます。
<< >> は約1°< > は約0.1°刻みでサーボ位置を変更できます。
キャプチャーボタン はUSBやFlashAirでロビに接続している時にロビの姿勢をキャプチャーしてロビモーションシミュレーターに取り込みます。
はUSBやFlashAirでロビに接続している時にロビの姿勢をキャプチャーしてロビモーションシミュレーターに取り込みます。
ロビ2のプログラムを読み込んでいる場合は連携プログラムの赤外線受信に対応しているプログラムを動かす事ができます。
送信ボタン は現在のロビモーションシミュレーターのポーズを送信します。
は現在のロビモーションシミュレーターのポーズを送信します。
モーションエディターに接続している場合はモーションエディターとリモート接続している場合はモーションエディターのキャプチャーボタンでこのデータをポーズに取り込めます。
USBやFlashAirでロビに接続ている場合はロビのポーズをロビモーションシミュレーターの画面に合わせます。
ロビ2のプログラムを読み込んでいる場合は連携プログラムの赤外線送信に対応しているプログラムを動かす事ができます。
中央の3つのボタン

 はロビの姿勢を変えます。
はロビの姿勢を変えます。
実物のロビと同じ直立(原点)、床座り、充電チェアー座りの3つの基本姿勢でプログラムはこの姿勢に合わせて実行されます。
オプションパーツ(parts19.stl)が提供されている場合は充電チェアー座りで充電チェアーが表示されます。
一番上のスライダーで画像全体が回転されている場合は正面にリセットされます。
一番右の2つのボタン
 は人感センサーのON/OFFを切替えます。
は人感センサーのON/OFFを切替えます。
押すとセンサーが感知した状態になりもう一度押すとOFF状態となります。
両方ON状態の場合は両方のセンサーが感知した事になります。
リモート接続時のメインプログラムで顔の向きを変えたり留守番プログラムで侵入者の発見に機能します。
ロビ2の場合は左右のセンサーの代りに次の2つのボタンが表示されます。
 はロビ2のカメラが顔を認識した事をシミュレーションします。
はロビ2のカメラが顔を認識した事をシミュレーションします。
認識語「防犯モード」または「メッセージ伝えて」で顔を認識させる場合はこのボタンを押して下さい。
STARTUP.BINを読み込んだ状態(プログラムは開始しない)でこのボタンを押すとアイドリング時に顔を認識した場合の動作をシミュレーションします。
なお認識するのは1番に登録したユーザと認識します。(メッセージがある場合はそのユーザを認識します)
またユーザが登録されていない状態ではディフォルトのユーザとして認識されます。
 はロビ2の頭のスイッチをシミュレーションします。
はロビ2の頭のスイッチをシミュレーションします。
実際のスイッチと同様、プログラムの実行中にこのボタンを押すと押すとプログラムを中断する事ができます。
STARTUP.BINを読み込んだ状態(プログラムは開始しない)でこのボタンを押すとアイドリング時にロビ2が言う独り言をシミュレーションします。
ロビの大きさや位置をマウス操作で変更する事ができます。
ロビの大きさはマウスのホイール操作で変更できます。
ホイールを前に回すと大きくなり後ろに回すと小さくなります。
ロビをドラッグ(マウス左ボタンを押してマウスを動かす)すると画面内の位置を変える事ができます。
なお変更した大きさや位置はリサイズコマンドやを本プログラムの再起動で元の大きさと位置に戻ります。
本プログラムのウィンドウ全体の大きさをマウス操作で変更する事ができます。
画面の右下をマウスでドラッグして大きさを調整してください。
表示されるロビの画像は画面の大きさに応じて変わります。
画面の縦横比によってロビの縦横比も変わりますのでウィンドウの大きさが決まったらリサイズコマンドを行ってください。
表示メニューのリサイズコマンドまたはツールバーの でロビの大きさを現在のウィンドウの大きさに合わせてサイズします。
でロビの大きさを現在のウィンドウの大きさに合わせてサイズします。
ファイルメニューの設定ファイル再読込コマンドまたはツールバーの で設定ファイルのパーツ情報を読み直し3D画像を再表示します。
で設定ファイルのパーツ情報を読み直し3D画像を再表示します。
ファイルメニューのリモート開始コマンドまたはツールバーの でリモート接続を開始します。
でリモート接続を開始します。
ファイルメニューのリモート終了コマンドまたはツールバーの でリモート接続を終了します。
でリモート接続を終了します。
ファイルメニューのマスター接続コマンドまたはツールバーの でマスターとしてリモート接続されます。
でマスターとしてリモート接続されます。
マスターとしてリモート接続されるとサーボファイルとキャプチャーファイルの扱いが逆になります。
ロビモーションエディターをふたつ立ち上げておいて片方をマスター接続にするとマスター側から送信されたポーズを片方のロビモーションエディターが再生することができます。
またマスター接続の場合、ロビボイスエディターなどとリモート接続をした場合、リモート接続ファイルに対して既読更新しませんので複数のシミュレーターを同時にリモート接続で動かす事ができます。
なおマスター接続に切り替えると同時にリモート接続が自動的に開始されます。
ロビモーションエディターとの連携についてはこちらを参照してください。
ファイルメニューの画面のキャプチャーコマンドまたはツールバーの は表示中の画面をそのままキャプチャーして画像ファイルに書き込みます。
は表示中の画面をそのままキャプチャーして画像ファイルに書き込みます。
作成できる画像ファイルはJPEGファイルまたはビットマップファイル(BMP)でJPEGファイルはそのままSNSに投稿できます。
ファイルメニューのプログラムを開くコマンドまたはツールバーの でロビのプログラム(.RM4または.BIN)を読込みます。
でロビのプログラム(.RM4または.BIN)を読込みます。
ロビ2のプログラムはSTARTUP.BINとうファイル名ですが本プログラムで書き出したバイナリプログラムも読込む事ができます。
ロビ2のプログラムを読込む場合は、ファイルの種類をバイナリプログラムに切り替えてください。
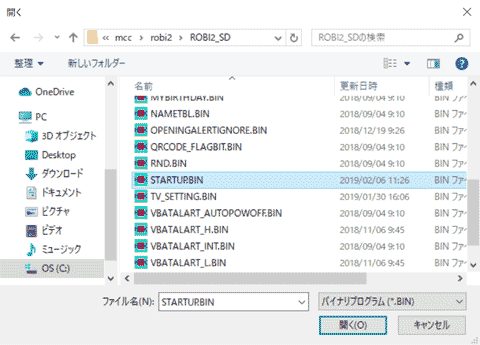
プログラムメニューのプログラムの開始コマンドまたはツールバーの でロビのプログラムの実行を開始します。
でロビのプログラムの実行を開始します。
プログラムを終わりまで実行したら自動的に停止します。
ロビ2のSTARTUP.BINを実行した場合は、最初に音声認識ダイアログが表示されるので実行する音声認識語を指定してください。
ロビモーションランナーを使うと複数のロビモーションシミュレーターに読み込んだプログラムを一斉に実行する事ができます。
この場合ロビ2の音声認識ダイアログは表示されずに最後に実行した認識語のプロクラムが実行されます。
プログラムメニューのプログラムの停止コマンドまたはツールバーの でロビのプログラムの実行を停止します。
でロビのプログラムの実行を停止します。
プログラムの途中で停止させる事ができます。
プログラムメニューのプログラムのステップ実行コマンドまたはツールバーの でロビのプログラムを1ポーズのみ実行します。
でロビのプログラムを1ポーズのみ実行します。
ポーズ以外の命令は続けて実行します。
停止コマンド停止させた時はその続きのポーズから実行します。
リモート接続している場合はポーズをロビに転送します。
プログラムメニューのプログラムのデバッグコマンドまたはツールバーの でロビのプログラムをデバッグする事ができます。
でロビのプログラムをデバッグする事ができます。
デバッグ操作の詳細についてはこちらを参照してください。
なおデバッグ機能はロビ2のプログラムに対しては行う事はできません。
プログラムメニューのプログラムのモーション作成コマンドまたはツールバーの でロビのモーションプログラムを作成する事ができます。
でロビのモーションプログラムを作成する事ができます。
モーション作成の詳細についてはこちらを参照してください。
プログラムメニューの直接実行コマンドで現在開かれているロビのプログラムをリモート接続されたロビに転送して実行する事ができます。
この機能を使うにはロビ(ロビ2は未対応)がUSBまたはFlashAirでPCに接続されている必要があります。
なお直接実行を行う時はリモート接続は終了状態でなければいけません。
また直接実行でロビを動かした場合は停止コマンドで終了させる事はできません。
なおロビ2は直接実行を行う事はできませんで。
設定メニューの原点設定コマンドでロビの設定ファイル(STARTUP.XML)の原点補正値を読込みシミュレーション画像の原点とすることができます。
なお原点が変更された場合、それ以降にモーション作成機能で作成されたモーションプログラムは読み込んだ設定ファイルを使用しているロビでしか正常に動かす事ができません。
設定メニューのパーツ取外しコマンドまたはツールバーの でロビのパーツを取外し色が変更できます。
でロビのパーツを取外し色が変更できます。
設定メニューの目色変更コマンドまたはツールバーの で目のLEDの色が変更できます。
で目のLEDの色が変更できます。
カラーダイアログが表示されますので色を指定してください。
目の色はプログラムで設定されるためここで設定された色はプログラムが動いていない時にセットされます。
表示メニューの口色変更コマンドまたはツールバーの で目のLEDの色(ONの時)が変更できます。
で目のLEDの色(ONの時)が変更できます。
カラーダイアログが表示されますので色を指定してください。
また実際のロビの口のLEDは赤く光りますがシミュレーターでは赤以外も表示することができます。
口のLEDを消灯する時はカラーダイアログのキャンセルボタンを押してください。
なお口のLEDの消灯時はパーツの色で設定された色になります。
設定メニューの背景色変更コマンドまたはツールバーの で背景の色が変更できます。
で背景の色が変更できます。
カラーダイアログが表示されますので色を指定してください。
なお背景の色を設定すると画像ファイルが背景に設定されている場合は設定がクリアされます。
表示メニューの正面/側面/背面コマンドまたはツールバーの


 でロビの方向が切り替えられます。
でロビの方向が切り替えられます。
平面コマンドまたはツールバーの でロビの真上からのカメラに切替えられます。
でロビの真上からのカメラに切替えられます。
平面コマンドは移動シミュレーションの設定時のみ実行できます。
目線カメラコマンドまたはツールバーの でロビの目線カメラに切替えられます。
でロビの目線カメラに切替えられます。
目線カメラコマンドは移動シミュレーションおよびターゲット表示設定時のみ実行できます。
なおターゲットが離れている場合は何も表示されない事があります。
プログラム操作
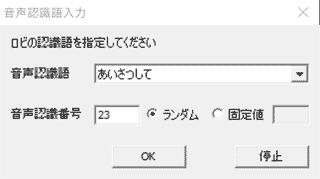
ロビのプログラムのシミュレーションで音声認識のコマンドがあると音声認識語ダイアログが表示されます。
音声認識語のコンボボックスから認識語を選択してください。
また認識番号を直接キーボードから入力する事もできます。
認識番号は1〜278の数字を入力してOKボタンを押して下さい。
数字と認識語の対応はNinshiki.csvファイルで確認してください。
プログラムで受け付けられる認識語を入れないと繰り返して認識語を聞いてきます。
なお音声認識語リストを選択した場合はOKボタンを押さなくても認識語を返します。
停止ボタンを押すとプログラムの実行は停止されます。
ランダムと固定値のラジオボタンはランダムで動くプログラムのランダム値を固定にする事ができます。
ランダム値を固定にする事によって毎回同じ動きにする事ができます。
固定値は0〜Xで指定しますがXの値はプログラムで異なりますが大きい値を設定しても各プログラムで選択値にまるめられるので任意の数字で構いません。
留守番プログラムのような人感センサーを使うプログラムではコントロールダイアログのセンサーボタンで操作する事ができます。(ロビ1のみ)
ロビ危機一髪プログラムのようなロビの体を動かして遊ぶプログラムではコントロールダイアログのスライダーで操作できます。
この時、スライダーでシミュレーション画面を動かす事ができますがプログラムによりすぐにパーツが元の位置に戻されてしまいます。
絵本を読ませるプログラムを実行すると次のダイアログが表示されるので読ませる絵本とページ番号を指定してください。
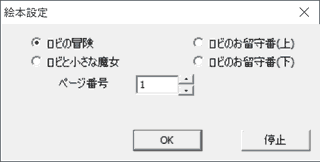
絵本を読ませるプログラムを実行するにはまずコントローラーの  で充電チェアーに座らせてから認識語「絵本読んで」で実行させる事ができます。
で充電チェアーに座らせてから認識語「絵本読んで」で実行させる事ができます。
次に認識語「はい」を答えると上記のダイアログが表示します。
絵本を読んでいる途中に を押すと朗読を中断して違うページが指定できます。
を押すと朗読を中断して違うページが指定できます。
メッセージを登録プログラムを実行すると次のダイアログが表示されるのでメッセージを伝える相手とメッセージの番号を指定してください。
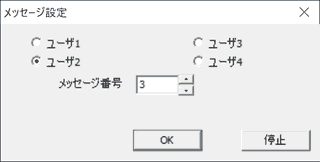
メッセージを登録プログラムを実行するには認識語「メッセージ伝えて」で実行させる事ができます。
次にコントローラーの を押して顔を認識させてください。
を押して顔を認識させてください。
なおこの時はユーザ番号1に登録されたユーザを認識します。
またユーザが登録されていない状態の場合はディフォルトのユーザとして登録されます。
上記ダイアログで指定する番号にユーザが登録されていない場合はをディフォルトのユーザが相手として登録されます。
メッセージ番号は下記の順番で1〜10の数字で指定します。(Robiブックと順番が違います)
おつかれさま,おかえり,元気だして,お手伝いして,おやつあるよ,ありがとう,がんばってね,おめでとう,だいすきだよ,ごめんない
メッセージはSTARTUP.BINを読み込んだ状態(プログラムは開始しない)でコントローラーの を押すと伝えてくれます。
を押すと伝えてくれます。
QRコードを読ませるプログラムを実行すると次のダイアログが表示されるのでQRコード番号を指定してください。
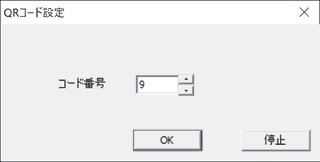
QRコードを読ませるプログラムを実行するには認識語「メール読んで」で実行させる事ができます。
QRコード番号はパワーアップの回数とは違っていて画像認識ボードで認識したQRコードの番号で1〜48の数字で指定します。
なお途中使われていない番号もありますがその場合は何も実行せずは再びダイアログが表示されます。
またすでにパワーアップ済のQRコードに対してもパワーアッププログラムは実行されます。
ロビ2のプログラムを読み込んだ状態でコントローラーの または
または を押すと次のダイアログが表示されるので赤外線コードを指定してください。
を押すと次のダイアログが表示されるので赤外線コードを指定してください。
ふたつのボタンのどちらを押しても構いません。(ラジオボタンの初期値が違ってきますが切替える事ができます)
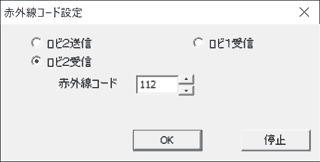
ロビ2送信はロビ2が赤外線コード(112〜127)を送信する時に対応するプログラムをシミュレーションします。
ロビ2受信はロビ2から送信された赤外線コード(112〜127)を受信した時に対応するプログラムをシミュレーションします。
ロビ1受信はロビ1から送信された赤外線コード(65〜72)を受信した時に対応するプログラムをシミュレーションします。
ロビ2送信とロビ2受信で同じ赤外線コードを指定するとそれぞれを連携させる事ができます。
ロビ1受信は赤外線コード(65〜72)はロビ1のロビリンクのプログラム(ロビ1_ロビ2_パターン0x0_TX.RM4〜ロビ1_ロビ2_パターン0x7_TX.RM4)に対応しています。
なお連携プログラムはダイアログのOKボタンを押されると直ちに実行が開始されるので実際にロビから送信された赤外線を受信するタイミングが異なります。
ロビモーションシミュレーターは背景をプログラムで制御できるようにロビのプログラムを拡張しています。
コマンドの仕様やプログラムの変更方法はこちらを参照してください。
リモートコントロールダイアログ
移動シミュレーションを設定するとリモートコントロールダイアログが表示されてロビをボタン操作で移動させる事ができます。
移動プログラムを動かすた移動プログラムを入れたフォルダーをパラメーター設定で指定しておく必要があります。
連続歩行.RM4は標準のプログラムではないのでのこちらダウンロードしてください。
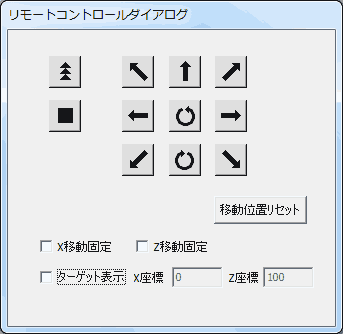
操作ボタンでロビを動かす事ができます。()はボタンに割り付けられたプログラムを表します。
 停止ボタンを押すまでロビが前進します(ADDON/連続歩行.RM4)
停止ボタンを押すまでロビが前進します(ADDON/連続歩行.RM4)
 連続歩行を停止します
連続歩行を停止します
 左方向に前進します(歩行左4S.RM4)
左方向に前進します(歩行左4S.RM4)
 前進します(歩行4S.RM4)
前進します(歩行4S.RM4)
 右方向に前進します(歩行右4S.RM4)
右方向に前進します(歩行右4S.RM4)
 左に方向転換します(左方向転換.RM4)
左に方向転換します(左方向転換.RM4)
 左旋回(反時計回り)します(旋回左1.RM4)
左旋回(反時計回り)します(旋回左1.RM4)
 右に方向転換します(右方向転換.RM4)
右に方向転換します(右方向転換.RM4)
 左方向に後進します(後退左向き.RM4)
左方向に後進します(後退左向き.RM4)
 右旋回(時計回り)します(旋回右1.RM4)
右旋回(時計回り)します(旋回右1.RM4)
 右方向に後進します(後退右向き.RM4)
右方向に後進します(後退右向き.RM4)
移動位置リセット ロビの移動位置と角度を原点に戻します
X移動固定 X方向(正面カメラで左右)を固定して表示ます。(ターゲットが表示されている場合はターゲットが移動します)
Z移動固定 Z方向(正面カメラで前後)を固定して表示ます。(ターゲットが表示されている場合はターゲットが移動します)
ターゲット表示 オプションパーツをターゲットとして表示されます。オプションパーツがない場合は表示されません
X座標,Y座標 ターゲットの表示位置を指定します
パラメータ設定
パラメータ変更を行う場合は設定メニューのパラメーター設定コマンドで行ってください。
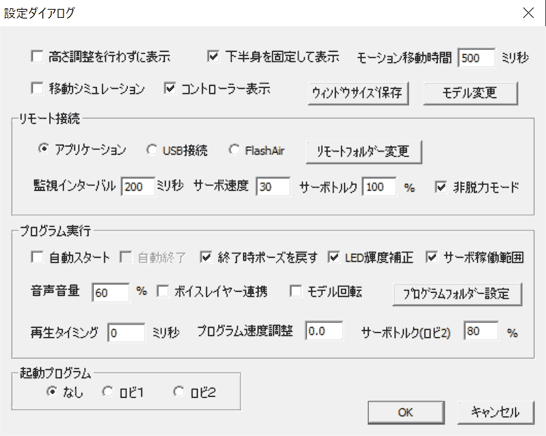
高さ調整を行わずに表示をチェックすると足の位置に関係なく画面の中心に腰の位置が来るように表示されます。
チェックを付けないと足の角度によって画像の位置を調整します。
下半身を固定して表示をチェックすると腰のサーボの回転で上半身が回転して表示されます。
チェックを外すと逆に下半身が回転して表示されます。
モーション移動時間は基本姿勢に戻す時の速度でミリ秒で指定します。
ロビのポーズをキャプチャーした時もこの速度で取り込んだポーズにします。
移動シミュレーションをチェックすると歩行プログムによりロビが移動した位置と角度をシミュレーションする事ができます。
この設定をするとロビを動かすためのリモートコントローラーが表示されます。
コントローラーの操作方法はこちらを参照してください。
なおロビの歩行プログラムを音声認識などの通常の方法で動かしてもシミュレーションする事ができます。
コントローラー表示は本プログラムの起動時にモーションコントローラーを表示するどうか指定します。
コントローラーは表示コマンドで表示非表示を切り替えられますがプログラムを実行するだけの場合などチェックを外しておきます。
サーボトルクはリモート送信およびプログラム(含む直接実行)の書出し時のサーボのトルクを指定します。
足と足以外のトルクをそれぞれの値で指定できます。
リモート送信のサーボトルクは上側の値で指定します。
ウィンドウサイズ保存ボタンはウィンドウサイズを設定ファイルに書き込んで次回から現在のウィンドウサイズで起動されるようになります。
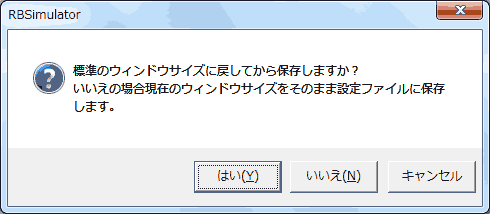
質問に「はい」を答えると標準のウィンドウサイズに戻してから書き込みます。
標準の大きさから変更した場合は「いいえ」を答えてください。
リモート接続設定
接続先はロビモーションシミュレーターのリモート接続する対象を設定します。
モーションエディターはWindowsのプログラムと接続する時指定します。
ロビモーションシミュレーター通しを接続する場合もこの設定です。
USB接続はUSBで接続されたロビに接続する時に設定します。
同様にFLashAirはFlashAirでロビに接続する時に設定します。
なおこれらの接続を行うにはリモート接続ができる環境が必要です。
監視インターバルはロビモーションエディターで書き換えられるサーボファイルを読込む監視時間をミリ秒で指定します。
サーボ速度はリモート送信時に送信するサーボ速度を指定します。
サーボ速度はロビのプログラムで使われている時間単位(1秒=60)で指定します。
トルクは通常のトルクに対するパーセンテージ(1〜100)で指定します。
ロビの場合サーボ毎にトルクが設定できますがすべてのサーボが指定した値になります。
この機能を使うにはリビジョン4.50以降のリモート接続用ロビプログラムをのロビに入れておく必要があります。
ロビ2でこの機能を使うにはロビ設定ファイルエディタ2でリモート接続用プログラムを組み込んでおく必要があります。
非脱力チェックはロビとリモート接続を行う場合にロビを脱力モードで動かすかどうかを設定します。
デバッグ機能やステップ実行でロビを動かす場合はこのチェックを付けてリモート接続を開始してください。
なお非脱力モードで動かすとサーボが動かなくなるのでロビのポーズを手で変更する場合はチェックを外してください。
フォルダー変更はリモート接続で読み込まれるリモートファイルをファイルダイアログで指定する事ができます。
リモート接続ファイルは最初のリモート接続開始の時に設定しますがフォルダー等を変更した場合は指定してください。
ADDONフォルダーのREMOTE.LOGを指定します。
サーボファイルやキャプチャーファイルもここで指定したフォルダーの物が使われます。
プログラム設定
自動スタートチェックはプログラムを開いた時や本プログラム起動時に引数でプログラムを指定した時や最後に開いたプログラムを自動的に実行します。
自動終了チェックはプログラムを引数で指定して自動スタートで実行したプログラムが終了した時にシミュレーターも終了します。
引数なしで実行した場合は自動スタートが設定されていてもパラメーターの変更ができなくなるためシミュレーターは終了しません。
他のWindowsアプリケーションで引数付きで本プログラムを起動した時に自動的に終了させる場合に設定してください。
終了時にポーズを戻すチェックはプログラムが終了した時にロビの姿勢を元に戻す時にチェックを付けます。
チェックがない時はプログラムの最後のポーズのままになります。
サーボ稼働範囲チェックはポーズ命令がサーボの範囲を越えた場合にサーボ範囲内に調整する時を付けます。
ロビのプログラムを他のモデルで動かす場合サーボの稼働範囲を越える場合があります。
モデル回転チェックはモーションコントローラーでモデルを回転をモーションデータに反映させます。
チェックがあるとモーション書出しでプログラムを出力する時に画像回転の角度をプログラムに書き出します。
サーボID1のデータとして書出すので実機でこのプログラムを実行しても実機には反映されません。
プログラム速度調整は使用するPCとロビのマイコンボードの性能の差によって再生時間がずれてきます。
それぞれのPCでずれは違ってきますので個々のPCで調整する必要があります。
この値はロビのプログラムのフォルダー4の0001分数える3.RM4(音声認識の場合1分タイマーを動かす)の処理時間を計測して実際のロビとずれた秒数を小数点以下1桁の値で設定します。
シミュレータの方が早く終わる場合は+の値を遅い場合は−の値で調整します。
実際のロビは「時間計って→1分」でこのプログラムを動かす事ができます。
こちらで実測したデータは58.5秒でしたが電圧等によっても変わってくると思いますので実際に動かすロビで計測してください。
なおプログラムによってずれる時間が違ってくるのでひとつの値ですべてのプログラムを完全に一致させる事はできません。
サーボトルク(ロビ2)でモーション作成で出力するロビ2のプログラムのサーボトルクが設定できます。
なおこの値はロビ1のRM4プログラムに書き出す時は無視されます。
ロビ1の標準プログラムのポーズのトルクは100%で設定されていますがロビ2の標準プログラムのほとんどのポーズは80%に設定されています。
音声音量はロビモーションエディターの音量を小さくする時に設定してください。
最大音量に対してのパーセンテージで指定してください。
100が最大で0が無音となります。
なお最大音量はWindowsのボリュームコントロールで設定している値に従います。
音声音量を0にすると音声の再生は行いません。
通常はチェックを付けますが音を出せない環境の場合、音声音量を0にしてください。
また本プログラムを立ち上げた時に音声デバイスの初期化でエラーが起こる場合は音声音量を0にすると音声デバイスに対する初期化は行いません。
ボイスプレイヤー連携にチェックを付けると音声認識命令に対して音声認識ダイアログが表示されません。
その代わりにロビボイスプレイヤーのリモート接続で認識語を本プログラムに送信してください。
ロビボイスプレイヤーと連携する場合はシミュレーターで動かすプログラムはリモート接続対応のものでなく必ず標準のものを使ってください。
ロビボイスプレイヤーとの連携についてはこちらを参照してください。
LEDの輝度補正チェックはプログラムを読み込んだ時にシミュレーターで表示される色をロビのLEDの色に近い色に補正します。
標準プログラムで指定されてるLEDの色は実際の色よりかなり暗いのでそのままシミュレーションすると黒く表示されてしまいます。
リモート接続時の送受信やモーションプログラムの書込みに時にLEDの輝度を抑制します。
このチェックを外すとそのままの輝度で処理を行います。
読み込んだプログラムのLEDの制御コマンドをそのまま処理したい時は外してください。
音声再生タイミングは音声の再生とロビの動きの同期を調整する時に設定します。
0の場合調整はしませんがプラスの値は音声の再生を指定した時間(ミリ秒)遅らせます。
プログラムフォルダー設定ボタンはCALL命令で呼び出すサブプログラムのフォルダーを指定します。
プログラムフォルダーのトップレベルのプログラムをどれか指定してください。
なおサブプログラムはロビのSDカード同様1〜9またはランダムファルダーに入れておいてください。
プログラムで呼ばれる音声ファイルや背景画像ファイルもこのフォルダーの下に置いておきます。
標準のプログラムを動かす場合は音声ファイルはロビのSDカード同様voiceフォルダーの下の同じフォルダーに入れておいてください。
起動プログラムを設定しておくと本プログラムが立ち上がるとそのプログラムが読み込まれます。
自動プログラムを設定しておくとそのプログラムがただちに実行されて実際のロビを立ち上げた時と同じ状態になります。
モデル変更ボタンで別のモデル設定ファイルを設定すると3Dモデルを他の物に切替える事ができます。
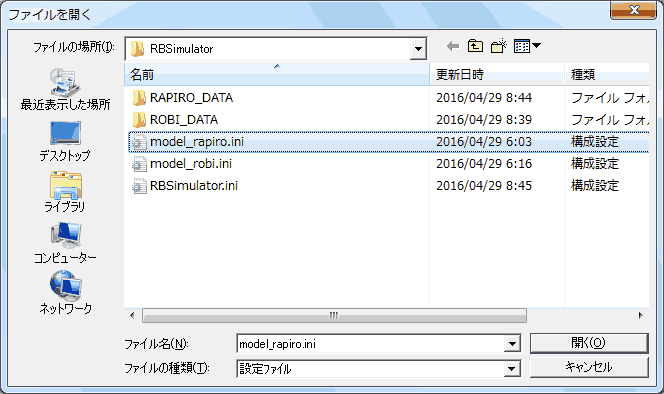
ファイルダイアログでmodel_xxxx.iniを指定してください。
モデルを切替えるには別のモデルデータをインストールしておく必要があります。
別のモデルデータはこちらからダウンロードできます。
別のモデルを設定した場合は本プログラムを再起動して表示モデルを切り替えてください。
背景設定
背景変更を行う場合は設定メニューの背景設定コマンドで行ってください。
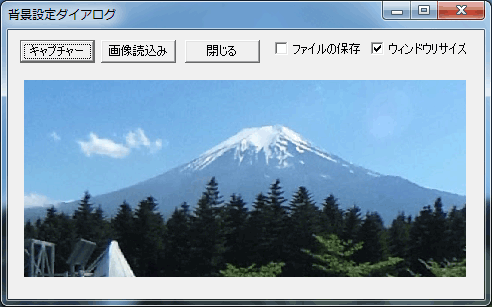
背景を設定するには次のふたつの方法があります。
ひとつは画像読込みボタンで背景画像を読込むことができます。
表示されたファイルダイアログに画像を指定します。
表示できる画像はJPEGまたはBMPです。
画像読込みボタンで背景画像を読込んで表示する事ができます。
表示されたファイルダイアログに画像を指定します。
表示できる画像はJPEGまたはBMPです。
もうひとつはディスプレィに表示中の他のプログラムの表示をキャプチャーして背景として取り込む方法です。
例えばストリートビューなどブラウザーで表示中の画像をそのまま背景に取り込むことができます。
本ダイアログの透明化されている部分に表示中の画像をそのまま背景になります。
この部分の移動は本ダイアログのタイトルバーをドラッグして動かします。
また本ダイアログの下、右端または右下の隅をドラッグすると本ダイアログの大きさが変わるのでそれに伴いこの部分の大きさが変えられます。
キャプチャーボタンを押すとそのまま背景として登録されます。
この時ファイルの保存をチェックしておくと任意のファイルに背景を保存しておく事ができます。
保存しなくても本プログラム再起動後も背景はそのまま保持されますが背景を切り替え後また設定する場合や他に使う場合は画像ファイルとして残しておけます。
キャプチャーする時や画像を読み込む時にウィンドウリサイズのチェックを付けておけばキャプチャーした画像や読み込んだ画像に合わせてウィンドウサイズを変更してくれます。
チェックを外しておけばウィンドウサイズはそのままで表示される画像の大きさはウィンドウサイズに合わせて拡大縮小されます。
この場合の縦横比は読み込んだ画像のまま保持されるため縦横比が合わない部分は表示されません。
また大きな画像を読み込む場合はこのチェックを外しておいてください。
背景のキャプチャー操作方法はストリートビューを使ったスナップの撮影方法(動画)も参考にしてください。
パーツの変更
 を押すとパーツの編集モードになりキー操作によりパーツの色を変更する事ができます。
を押すとパーツの編集モードになりキー操作によりパーツの色を変更する事ができます。
もう一度 を押すとパーツの編集モードは終了して設定ファイルに変更した色情報が書かれます。
を押すとパーツの編集モードは終了して設定ファイルに変更した色情報が書かれます。
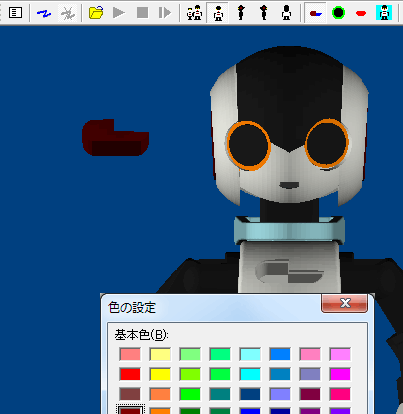
変更対象となるパーツはロビの体から外されロビの左横に表示されます。
この状態でキーボードから次のキーを入力する事でパーツを切替えたり色を変更する事ができます。
なお本プログラムのメインウィンドにフォーカスが当たっていないとキーが受け付けられませんので他のウィンドを操作した場合は本プログラムのメインウィンドのタイトルバーをクリックしてフォーカスを戻してください。
パーツの編集モードでは次のキーが有効です。
→←↓↑ 取り外すパーツの選択を変更します。→←はパーツ内の部品の選択を切替えます
1〜7 取り外すパーツの選択を変更します。1:頭,2:ボディ,3:腰4:右手,5:左手,6:右足,7:左足のそれぞれの先頭パーツを選択します。
同じキーを押し続けるとその部位内でパーツの選択を切替えます。
F1(ファンクションキー) カラーダイアログでそのパーツの色を変更します。
ここで設定される口のパーツの色は口LEDの消灯時の色となります。
F2(ファンクションキー) マテリアル設定ダイアログでそのパーツの光沢や色を変更します。
Home ロビの標準色に設定します。 Homeを押すと設定される標準色が切替わります。
Delete/BackSpace 現在設定ファイルに設定されている色に戻します。
Enter パーツ選択モードを終了します。  をもう一度押すのと同じ操作になります。
をもう一度押すのと同じ操作になります。
F2を押すと下のダイアログが表示されます。
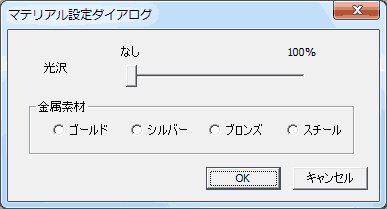
スライダーを動かすとパーツの光沢が変更されます。
通常のパーツはスライダーを一番左(光沢なし)に設定しておいてください。
下のラジオボタンは予め決めたられた金属の色が設定されます。
同時に光沢も最大に設定されますのでラジオボタンを選択するだけで金属パーツに変更する事ができます。
設定した色や光沢をパーツ情報設定ファイル(model_xxxx.ini)に書き込まれます。
カスタマイズしたパーツ情報設定ファイルを別のファイルにコピーすれば複数のモデルを作成する事ができます。
このパーツ情報設定ファイルはパラメータ設定のモデル変更ボタンで設定する事ができます。
またプログラム起動時に引数で指定する事もできます。
ダウンロード
本プログラムの最新版は以下のリンクからダウンロードする事ができます。
RBSimulator.zip
今まで提供していたWindows8/10の音声対策版を廃止しました。今までRBSimulator8.zipを使用していた方も上記のプログラムをそのままお使いください。
Windows8またはWindows10でインターネットからダウンロードしたプログラムを実行しようとすると「WindowsによってPCが保護されました」というダイアログが表示される事があります。
その場合はこちらの方法で実行する事ができます。












画像をクリックするとYouTubeに接続して動画を表示します。
Q-bo.zipQ-boモデルデータ
Robohon.zipRoBoHoNモデルデータ
Rapiro.zipRapiroモデルデータ
Gundam.zipガンダムモデルデータ
SDGndm.zipSDガンダムモデルデータ
Sample.zipサンプルモデルデータ
WRobo.zip女性型ロボットモデルデータ
Minion.zipミニオンモデルデータ
Doraemon.zipドラえもんモデルデータ
Skeleton.zip人体骨格モデルデータ
Aibo.zipAIBOモデルデータ
Asimo.zipASIMOモデルデータ
LRobi.zipROBIモデルデータ LIGHT版
本体プログラムと同じフォルダーに解凍してください。パラメータ設定で切り替えられます。
リモート接続用ロビプログラムの最新版は以下のリンクからダウンロードする事ができます。
Robi1.zip(ロビ1用)
Robi2.zip(ロビ2用)
なおロビのプログラム変更やSDカードの書き換えは、ロビ本体への影響を及ぼす可能性があるのであくまでも自己責任という事でお願いします。
また必ずオリジナルのSDカードのバックアップは取っておいてください。
問題があったらオリジナルのSDカードに戻してください。
ロビ2のリモート対応はロビ設定ファイルエディタ2を使って各自で行ってください。
ロビのプログラムはデアゴスティーニの通販サイトから購入する事ができます。
初版版、再販版、第三版の70号に付属するロビのココロ(SDカード)に収録されています。
ロビ2のプログラムは80号のロビ2ココロ(SDカード)に収録されていてこちらのサイトから購入する事ができます。
最大値の変更
プログラムサイズなどの最大値を変更する事ができます。
RBSimulator.ini(設定ファイル)をメモ帳等で変更してください。
セクション名、タグ名と値の意味は以下の通りです。
| [PROGRAM] | MAX_PROGRAM_SIZE | 最大プログラムサイズ | バイト数で指定 |
| [PROGRAM] | MAX_MOTION_COUNT | 最大モーション数 | |
実際にこのプログラムを動かした動画です。上記のリンクをクリックするとYouTubeに接続します。
ロビモーションシミュレーター
ロビモーションエディターとの連携
ロビモーションシミュレーター同士の連携
ロビとの連携
背景画像の変更
デバッグ機能
ストリートビューを使ったスナップの撮影方法
目次に戻る