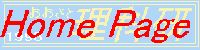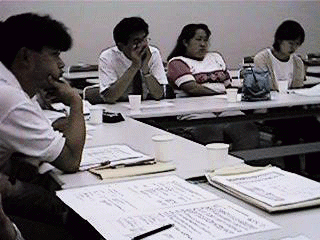
メダカはどうなったか? 子供たちは?!

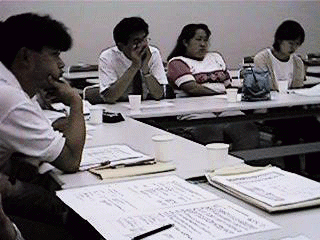
| 児童の反応
「かわいそう」「むりなんじゃない」 「僕もやりたい」「ペットボトルを持ってきたい」希望者をきくと50名集まる 「えさをあげたい」「えさをあげた方がいいんじゃないの」 「ふたをとりたい」 「死んだ原因を知りたい」「水が腐った替えたい」「池の水を入れたい」「川の水を取ってきたい」 「お墓をつくりたい」「家をつくりたい」 「自然のメダカをつかまえてきたい」 「さわってみたい」 「みたい、、けんかになる」 「日記をかきたい」「説明文をかく」「めだかでしりとり歌をつくる」「説明文を参考に飼育」 メダカの作文が普段の作文よりよくかける 「ほかの学年にあげたい」 「やりたくない」「先生はたよりにならない」 「どじょうでやってみよう」 |
| 飼育情報
その日に死亡 1/2 1週間以内で死亡 1/3 他は現在も生存 1週間以内で死亡 ほとんど 1ヶ月 生存 9本 2ヶ月生存 3本 2から6匹いりのものでは2から3匹が多くいき残る かめに飼っている水には微生物(食べ物)が多かった 3匹になった 5年で全滅 日光に当てるとphがあがる 8.5から8.9で透き通る 6.8で茶色のくもり 10.5で緑色の水で水草が溶ける お腹のへこんだメダカも日光に当てるとえさを食べて卵を産むようになった 水槽をたてにしたものとよこにしたものでは比べてもはっきり差がでない |
飼育面では 水はどうすればいいか 水草はどうすればよいか メダカはどうすればいいか 置く場所はどこがいいか 学習活動では どのように投げかけていけばいいか まとめはどうすればいいか 評価はどうすればいいか どのようにレポートをかかせればいいか |
「森は海の恋人」気仙沼に環境教育をたずねて   熊谷市立成田小 下妻淳志 平成10年7月31日気仙沼湾唐桑町牡蠣養殖地に到着すると、「森は海の恋人」の筆者、畠山重篤さんが 私達を待っていた。「森は海の恋人」とは、中学校3年生の国語の教科書に乗っている説明文で畠山さん は牡蠣の養殖を通して、環境教育を進めようとこの文を書き下ろしたということである。 早速、私達は梓の木でできた小船(あずさ丸)にのせてもらい牡蠣を養殖しているいかだへと向かった。 途中、交代で船を交代でこがせてもらったが「艪(ろ)」を使いこなすことはとても難しく、目的地にた どり着くことはなかなかできなかった。結局畠山さんの助けを借りていかだにたどり着くと、実際今育っ ている牡蠣を見せてもらった。1本のひもに20枚のホタテの貝殻をつるし、その1枚に30個の牡蠣種をつけ るという。計算すると1本で600個の牡蠣ができることになる。1つのいかだには150本つるしているので、 1個のいかだにできる牡蠣は、約90000個ということになる。それを2年間で育てるのだそうだ。いかだの 上に乗れたのも実際いい経験だった。海の上でのお話の後には、畠山さんのお宅でお話をうかがった。   
そこでの話は次のようであった。東京湾と鹿児島湾で魚介類の生産高をを比べると東京湾は鹿児島湾の 約20倍である。東京湾には汚れているというイメージがあるがその原因はいくつもの河川が流れていると いうことであるらしい。それだけ海の生物にとって川から流れてくる水の中の養分は大切だということで ある。牡蠣の養殖で有名な広島湾も気仙沼湾もおおきな河川が流れ込んでいる。気仙沼湾に流れ込んでい る大川の上流にダムが建設されるという計画が持ち上がったときに、学者らとともに畠山さんは反対した。 ダムがでできてしまうと森林からの多くの養分を含んだ土が海に流れ込まなくなり、海が死んでしまうか らである。土の養分は海の植物プランクトンをそだて、それをえさにしている動物プランクトンを育てる のである。広島湾では最近、流れ込んでいる太田川の上流にダムが建設されたために最近では生産高が伸 びていない。 そんな現状で畠山さんは海を守るためには山も大切なのだということを子供たちに訴えはじめている。 船にのせて海で話をしたり、いっしょに山に植林するなどの体験活動を通して、子供たちの口から親達に 自然界の関わり合いについてが伝わり、親の考えも変わってきているそうだ。近隣の農業が変わってきて いる例もある。環境教育を進めるためには、人間の生き方を問わなければならない。そのためには現象を 教えるだけでなく、子供たちの気持ちを転換させていかなくてはならないのだ。最近気仙沼湾はきれいに なり一時いなくなっていた生き物が帰ってくると同時に、夏はホタテ、秋には牡蠣というように、漁民の 生活が安定してきたために、若者までもが戻ってくるようになっている。という内容だった。 海のことを考えれば、山も考えなくてはならないという、自然界のつながりの大切さを私は改めて確認 した。また、「環境教育を進めるためには、人間の生き方を問うことだ」という言葉もとても印象的だっ た。話の中で畠山さんが何度も協調していたことは「環境のことを考えてくれる人間を育てなくてはいけ ない。そのためにもっとも大切なのは学校での教育なのだ。」ということだった。
|