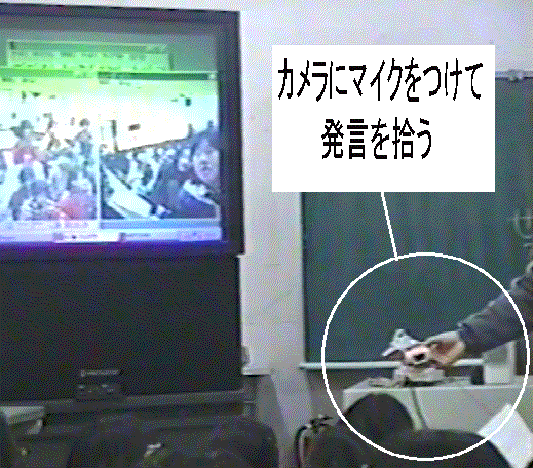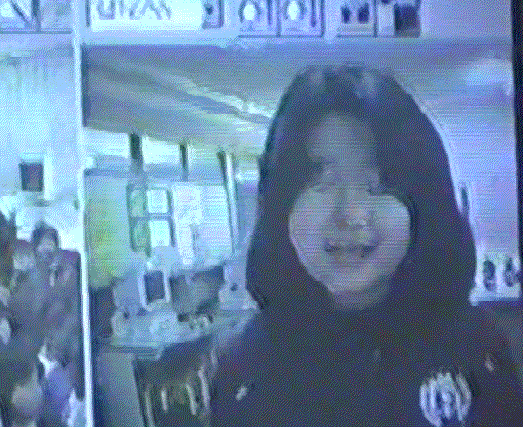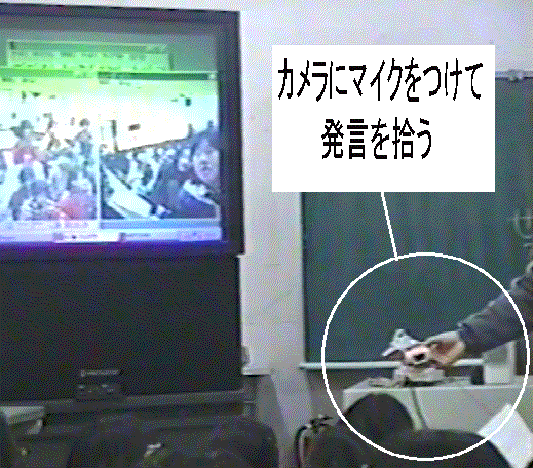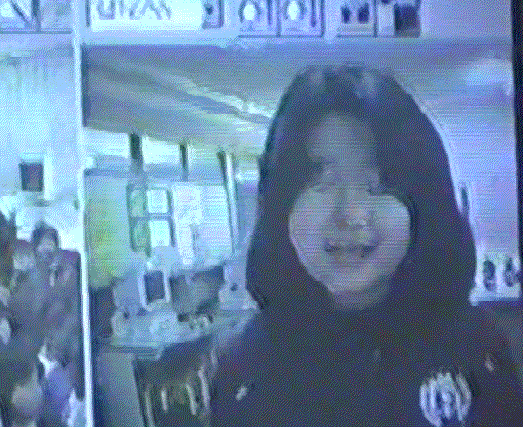TV会議による成果のある交流学習
1 はじめに
情報通信ネットワークの進歩により、授業やコミュニケーションが学級内から学校内そして学校外へと広がってきている。インターネットは世界を結び、人々との交流を盛んにしている。深谷市ではすでに4年前からテレビ会議システムフェニックスが導入され、授業で盛んに活用されてきている。各学校でもテレビ会議システムが導入され、様々な試みがなされている。その内容は博物館や専門施設の講師による遠隔授業型や離れた地方の様子をみる地域紹介型といったものが多い。テレビ会議システム自体の珍しさや性能を利用した学習では、研究発表や研究大会のイベントとして用いられるが、そのコミュニケーション教育的効果に関しては取り組まれているケースは多くない。テレビ会議を通して、今までの学習をバージョンアップし、成果を上げる試みが交流学習である。
2、交流学習の考え方
(1)遠隔地学習(沖縄の学校との交流、博物館などの講師の授業)
| →依頼 |
遠隔地の情報提供者
利益
奉仕の満足感 |
|
|
学習者
利益
専門知識 問題解決
遠隔地の様子
|
←承諾
←情報提供 |
| →質問 ※たとえば沖縄と埼玉で交流して も沖縄の学校にはほとんど利益が ないから続かない。 |
(2)交流学習
→依頼
|
|
学習者
利益
違う基盤にある意見
地域学校行事の情報 |
|
←承諾
←打ち合わせ→
←話し合い→
→共同宣言← |
|
学習者
利益
違う基盤にある意見
地域学校行事の情報 |
|
|
3、交流学習での注意点
交流学習を行う上で大切なことは、児童相互の情報交換によって、交流しなかったときよりも学習の質が高まるようにすることである。本活動では、普段教室で行われている道徳の時間よりも、交流学習によって相互に学習効果が高まることをねらっている。遠隔学習のように、どちらかが学習材をあたえるという一方向の学習ではなく、どちらの側にも利益がもたらされる効果を考えていきたい。たとえ距離は近くても学校や地域が違うと、行事や普段の環境が違い教室の中では出ないようなでないような考えそのために、交流学習の相手は以下のような点に気をつけた。
(1)同じ基盤に立って、平等に考えられること(今回は同じ学年)
(2)同じ情報を共有している(今回は同じ資料を学習している)
(3)同じ学習テーマで学習する(今、私たちにできること)
(4)違う経験をもっている(ボランティア体験や学校行事等)
(5)教師間の連携(本学習の趣旨に関する意思統一)
(6)児童同士の情報交流が円滑に進む授業構成にすること
4 授業実践(小学校 道徳 テレビ会議利用交流学習)
(1)主題名 人類愛
(2)ねらい
マザーテレサの業績について知り、ボランティア活動に興味を持ち、自分たちが できるボランティア活動とはどのようなことかを考え、自分の意見を持つ
(3)テレビ会議システム活用の意図
・となりの市の小学校(深谷市立明戸小学校)と意見交換をすることで、自分たち
の意見を的確に相手に伝える工夫を考える。
・相手校の意見を良く聞き、よく分からないときには詳しく質問して聞き取ろうと
する態度を育てる。
・自分たちの意見と相手の意見の良いところ足して、今までより良い活動を考えよ
うとする態度を養う。
(4)準備
資料「マザーテレサ」のプリント資料
インターネットメール
NTTテレビ会議システム
(5)学習計画(3時間扱い)
|
|
資料を使った学習 各教室 通常の道徳の授業を行う
自分たちの意見をインターネットで交換 1時間 |
|
↓
|
|
テレビ会議を使った意見交換(資料を読んでの意見交換)
相手校との意見交換の後のクラス内での話し合い(作戦タイム)
テレビ会議を使った意見交換(私たちにできることの意見交換) 1時間 |
|
↓
|
|
自分たちで考える私たちにできることの話し合い
インターネットメールを使っての結果報告 ボランティア活動の計画 1時間 |
|
(6)展開
| |
学習活動 |
時間 |
留意点 |
A
|
・インターネットでマザーテレサについて調べる
・資料「マザーテレサ」を読む
・マザーテレサの業績について話し合う
・自分を振り返る
・授業の様子をメールで明戸小に送る
・明戸小からのメールで意見を聞く。
・自分たちでできるボランティア活動について考え話し合う。
・話し合いの様子から自分の意見をまとめておく
・メールで様子を知らせておく |
45分
30分
|
・本時について、マザーテレサの基礎知識を持つ。
・マザーテレサが人のためにしていることを考えさせて、自分にできることから始めていることに気づかせたい。
・自分たちの生活を振り返って、困っている人に何かしてあげた経験があるかを話し合わせたい
・数人の意見をメールで送り、意見交換の材料にする。
・意見交換する事を伝え、ある程度クラスでまとめておくことを意識させる。
・3つくらいにまとめておく、その内容に責任をもって話せるようにしておきたい
・教師が児童の考えを評価して堂々と言えるように自信をつけさせる
|
B
c
|
・明戸小とテレビ会議でつなぐ
○お互いクラス代表があいさつ今までの経過について話し合う
○感想を話し合う
○私たちにできることを話し合う
○相手に質問する
|
20分
|
・はじめは名前をカードに出して、自己紹介的に話す。なれてきたら○○さんというように相手の名前で話し合いができるようにしたい。
・聞き取れないときは「聞こえません」とか「もう一度言ってください」といいはっきりと相手の意見を聞き取り、受け止めてから話すようにしていきたい。
・質問するときは、相手の話に対して質問し、相手がそれに答えていないときはもう一度聞かせるくらいのはっきりとしたコミュニケーションをさせたい |
○私たちにできることを話し合う
○フリートークで質問や意見を話し合う。
○やることの具体的な手順を確認して会議を終わりにする |
20分
|
・具体性がもてるような話し合いに変えていく。
・テレビ係の教師以外に、話し合い担当の教師が児童の話し合いの良いところを支援したり、舵取りをしながら、結論に向けていきたい。
・できるだけ円滑に話し合いが進むようにテレビを動かして児童の意見を拾って相手に伝えたい
・お互いにあいさつをする |
| |
私たちにできることを決めていこう(ネパールに鉛筆を送る) |
|
○感想をメールで送る
|
45分
|
・具体的な方向に進めるように、質問や意見を交換し満足感を持たせたい
・話したりなかったことはメールで送っておく
|
5 テレビ会議による話し合いの経過
(1)指導体制(ティームティーチング)
① カメラ担当 染谷明信
CCDカメラにマイクをつけて担当教師が持ち歩き、発言している児童の顔をアップでとらえるとともに、声を拾う。児童は画面の前に座り、自由に発言する。カメラ担当の教師が発言させる児童を決めて、発言させる。相手の話に対する反応も拾う。
②話し合い担当 関根達郎
児童同士の話し合いを活性化する。発言に対してはその場で「いいぞ」「もっと詳しく聞いて!」等、評価と支援を行う。聞こえない時は「聞こえません」とか、中途半端な会話になっている時は、児童に「もう一度話して」と心のコミュニケーションの手助けをする。
(2)話し合いの概要
○ 籠原小サイド
教師「つなげましたこれから会議を始め
ますよろしくお願いします」
児童a「私は籠原小学校のaです。私たちのクラスでマザーテレサについて話し合ったことについて何人か意見を言いますそちらの意見も聞かせてください」
児童b「マザーテレサはすばらしいと思います。自分のことを考える前に困っている人のことを考えているからです」
(中略)
児童c「では私たちのクラスで考えた私たちにできることを発表します。まず私たちにできることは人に平等にすることだと思います」
児童d「僕たちもJRCで募金をしています。」
(中略)
児童e「どんな鉛筆でも良いのですか」
児童f「短いのでもいいのですか」
児童g「短いものでも気持ちが伝わればいいのではないのですか」
児童h「どうしてもいけないのですか」
(後略) |
|
○明戸小サイド
教師「お願いします」
児童A「私もマザーテレサはすばらしいと思います。自分のお金をいろいろな人に与えてすばらしいと思います。」
(中略)
児童B「困っている人に声をかければいいと思います」
児童C「自分たちで募金をすればいいと思います」
(中略)
児童D「明戸小では毎年ネパールに鉛筆を送っています」
児童E「自分たちでよういできるものでいいのです」
児童G「使ってあるものはちょっとよくないです」
児童H「そうれはそうなんですけど、今までは使っていないものにしています」
児童I「今度聞いてみます」(後略) |
|
6 学習の成果
・児童ははじめ緊張していてもだんだんなれると会話できるようになる
・2点間の会話(テレビ会議)をクラス全員で見て、よりよい会話になるように良く聞
いたり、質問するコツを指導でき、子どもたちは会話は、相手の話を聞くことが大切
だと言うことがわからせることができた。
・相手に話を伝えることの難しさや、反応することの大切さを実感できた。
・相手の学校の考え方の違いで、ボランティアに対する考え方が広がった。
・ネパールに鉛筆を送る活動を知り、具体的なボランティアの方法が分かり、参加した
いという意欲が高まった(籠原サイド)
・相手校にも自分の学校の活動を指示され、さらに活動が活発になった(明戸サイド)
・籠原小ではテレビ会議をした6年2組が学校全体にこの活動を広めるために、宣伝の
チラシを作ったり、全校に呼びかけ700本以上の鉛筆が集まった。
8 今後の課題
今回の取り組みは、相手校に恵まれ、計画の段階でうまく共通理解が図れたが、詳しい企画書やノウハウ、評価の規準等をはっきりさせて、テレビ会議が日常的に有効なメディアとして学校に定着するためによりよい年間計画等が必要になってくると思われる。
また、発達段階に応じた指導や、国語等の学習で定期的に交流できる相手校との連携を作って行くことが大切であると考えられる。