情報を「核」にする「総合的な学習」の実践の情報教育的考察
熊谷市立籠原小学校 教諭 関根達郎
1、はじめに
学校現場で、総合的な学習の時間の試行が始まった。そのテーマに「情報教育」を掲げるものは少なくないが、パソコンの使い方を学ぶという例が多いようである。情報教育を軸にする場合、パソコンを含む情報機器を効果的に使って、豊かな学習活動し、情報活用能力を育成する形(コンピュータ等をてこに)と、情報社会を教材化し、情報に対する見方や考え方を学ぶ形(情報を柱に)が考えられる。本実践は前者を扱っている。学校行事(移動教室)に際して、自分の調べたいことを様々なメディアを使って調べ、その後、移動室に臨み、情報と実際の様子とをくらべる。さらに行ってきた感想を織り交ぜ、自分の学習テーマについてまとめ、いろいろな人に紹介する。情報収集-体験-情報発信という一連の流れの中で情報活用能力を育成していくという学習である。こうした活動を通して、児童はどのように情報をとらえ、どのようなことを学んでいくかを探りたい。(情報を核にした学習)

今年度、本校でも35時間の試行を行った。本実践では学年内T.T.(陸名佐知子教諭、笠越基江教諭、堀口芳嗣教諭)のもとで海浜学校、修学旅行と言った学校行事を絡めた学習計画を組んでいる。一部の書籍で「安易に学校行事をからめてはいけない」と報じられているが、本実践は安易に行事の事前指導を総合的な学習の時間に振り替えたのではなく、文部省教科調査官 北俊夫氏が著書の中(1999「総合的な学習とこれからの学校・授業づくり」光文書院)で提案しているタイプⅢ 教科等との並行(並列)型およびタイプⅤ 総合的な学習によるサンドイッチ型を参考にして構成している。本実践を通して今後の情報教育と総合的な学習の時間の在り方を探っていきたい。
2 本実践の基本的な考え方
3、学習活動案(教師が児童に示した学習の流れ)
総合的な学習の時間「調べてみよう比べてみよう」(18時間)
4、授業実践(実際の児童の活動)
(1) 児童の学習の経過 学習テーマ
鶴岡八幡宮 円覚寺 高徳院 銭洗弁天等 熊谷vs鎌倉
どんなお寺があるか 切り通しとはなにか
大仏を調べたい 鎌倉の小学生と交流したい
江ノ電や交通システムにのってみたい
江ノ島近くの海でどんなことが行われているのだろう
鳩サブレーについてしらべたい。 昔の食べ物と今の食べ物
鎌倉名産の食べ物の作り方 等 他9
|
(2) 児童の変容
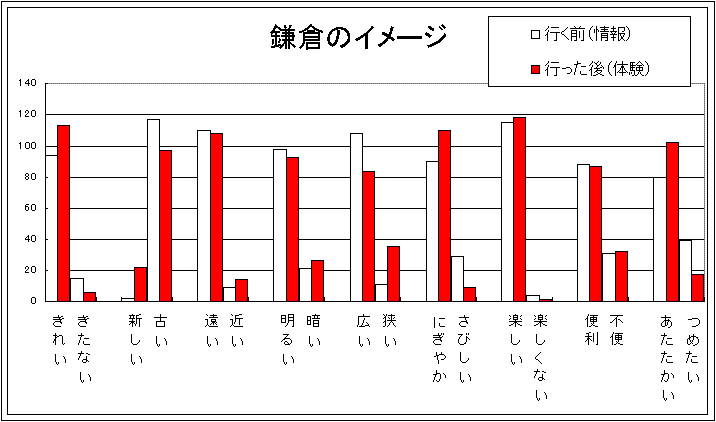 ①調べた情報(二次情報)による鎌倉に関するイメージと行った後(体験情報)の比較
①調べた情報(二次情報)による鎌倉に関するイメージと行った後(体験情報)の比較
鎌倉という未知の土地について、ガイドブック等にのっている情報は、情報を作った人の意図が大きく関わっている。調査の中「あたたかい」というイメージについては情報で現れない現地の人とのふれあいでたと
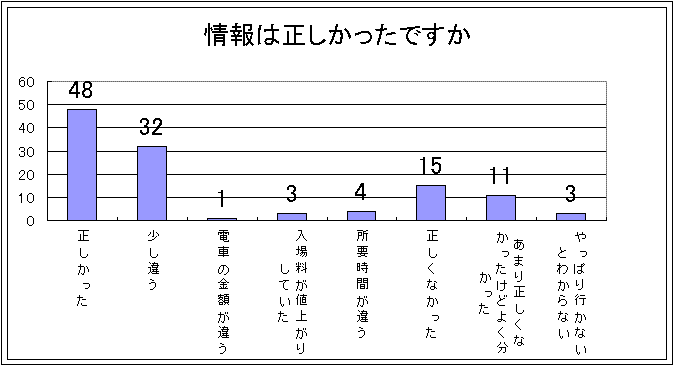
いうことが分かった。
②情報の信憑性に関する意識
情報を実際に検証する機会を持つことによって、情報に関する見方が変化している。正しくなかったと言う児童の中には、「これからはいくつかの資料を比べたい」と言う声が出ていた。
③ 自己評価 (学習を通して、児童が感じたこと、身に付いたこと)
知らないところでもガイドブックを見ると目的地につけると言うことが分かった。
鎌倉のお店の人はとても親切で、いろいろと聞くと教えてくれた。
八幡宮に直接電話をしていろいろ教えてもらった、電話のかけ方が勉強になった。
知らない人に話が聞けた。
いろいろな人の前で説明ができるようになった。
5年生やお母さんのまえで発表するのはドキドキしたができたこと。
人と話すことがとても大切なことが分かった。
自分で予定を立てて何かができるようになった。
みんなで情報交換などをやって詳しく分かるようになった。
計画のたて方が分かった。
マップだけでなく、人にも聞いて調べることは大切だった。
自分で行って、本に書いてあること以外のことを発見したこと。
みんなで協力して声を掛け合って話したりする事が大切だと思った。
やっぱり情報と本物はちがうんだなと思ったこと。
人に積極的に話しかけることができるようになった。
学校パソコンが自分で自由につかえるようになった。
今住んでいるところとずいぶん違うところがあるんだな と思ったこと。
人に頼まないで、自分で地図を見て歩いていろいろなことを確かめることができる |
|
|
「情報」の存在を意識しながら調査活動や発表を行っていくことで、情報に対する関心や正しく使っていこうという姿勢が見られるようになった。また、取材活動などを通して人との関わりのよさや体験する楽しさを実感している児童が多くいた。
④振り返りに関して(評価の方法)
発表会後、見に来てくれた父母と5年生から投票をしてもらった成果を集計し、さらに自分の活動を線結び方と自分でよくなったこととして振り返った。活動を客観的に振り返ることで、主体性がもてたかどうかを自分で確認することをねらって実施した。
5 まとめ
実践を通して、児童の変容が見られたことは、児童が主体的に学習を進めるようになったことである。児童の実態として自分たちで責任をもって準備や片づけができるようになったり、発表しようとしている姿は一番の収穫であった。情報に関してもいろいろな所から自分たちで探したり、人に積極的に関わろうとして集める良さを実感している様子が見られた。日頃、体験しないで物事を「めんどくさい」とか「つまらなそうだ」といって敬遠していた児童も「やってみようかな」「じぶんでもできるかな」という意識を持って学習にとりくむ姿が見られるようになった。意識して「情報」(2次情報)を扱う学習を重ねていくことで、情報社会の中で大切な「体験」(体験情報)の重要性を身をもって理解できているのではないかと思った。
6 今後の課題
1年目の実践で以下のようにな課題が見えてきた。
・児童のよりよいテーマ作り・児童の自分にあった目的別グループ作りの方法
・校外講師の協力体制 ・学年の指導体制・学年間の学習スキルの系統性
・体験活動の安全性 ・評価の方法・学習環境の充実等
総合的な学習の時間は、他の実践をまねるのではなく、児童の実態から話し合い、実践していく中から、よりよい形を教師が児童とともに作っていくことが大切だと実感した。今後さらに児童がよりよい方向に変容できるように実践を重ねてゆきたい。
 今年度、本校でも35時間の試行を行った。本実践では学年内T.T.(陸名佐知子教諭、笠越基江教諭、堀口芳嗣教諭)のもとで海浜学校、修学旅行と言った学校行事を絡めた学習計画を組んでいる。一部の書籍で「安易に学校行事をからめてはいけない」と報じられているが、本実践は安易に行事の事前指導を総合的な学習の時間に振り替えたのではなく、文部省教科調査官 北俊夫氏が著書の中(1999「総合的な学習とこれからの学校・授業づくり」光文書院)で提案しているタイプⅢ 教科等との並行(並列)型およびタイプⅤ 総合的な学習によるサンドイッチ型を参考にして構成している。本実践を通して今後の情報教育と総合的な学習の時間の在り方を探っていきたい。
今年度、本校でも35時間の試行を行った。本実践では学年内T.T.(陸名佐知子教諭、笠越基江教諭、堀口芳嗣教諭)のもとで海浜学校、修学旅行と言った学校行事を絡めた学習計画を組んでいる。一部の書籍で「安易に学校行事をからめてはいけない」と報じられているが、本実践は安易に行事の事前指導を総合的な学習の時間に振り替えたのではなく、文部省教科調査官 北俊夫氏が著書の中(1999「総合的な学習とこれからの学校・授業づくり」光文書院)で提案しているタイプⅢ 教科等との並行(並列)型およびタイプⅤ 総合的な学習によるサンドイッチ型を参考にして構成している。本実践を通して今後の情報教育と総合的な学習の時間の在り方を探っていきたい。
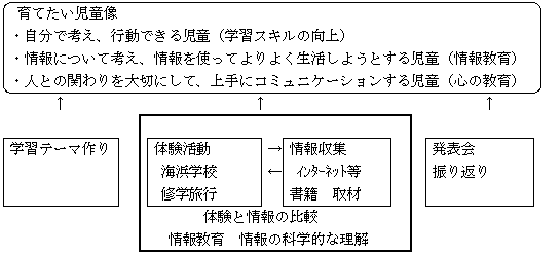
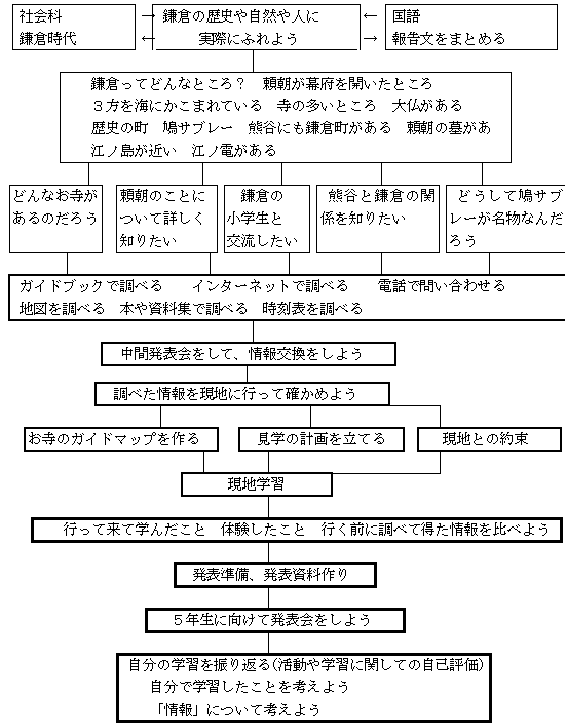
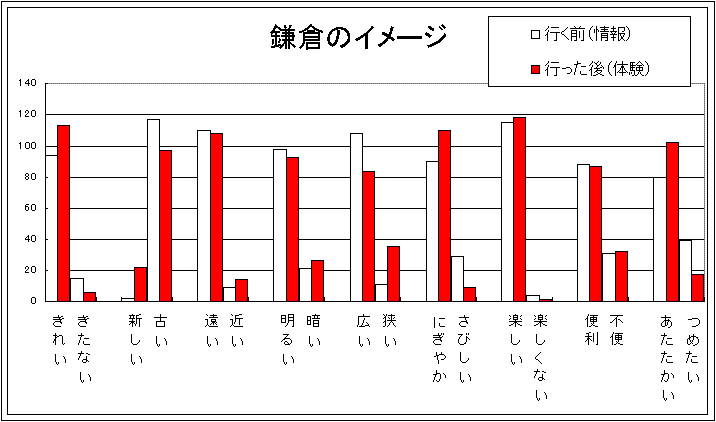 ①調べた情報(二次情報)による鎌倉に関するイメージと行った後(体験情報)の比較
①調べた情報(二次情報)による鎌倉に関するイメージと行った後(体験情報)の比較
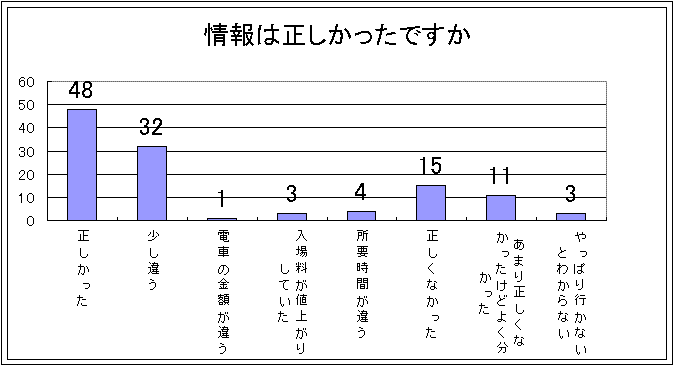 いうことが分かった。
いうことが分かった。