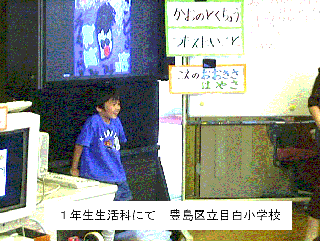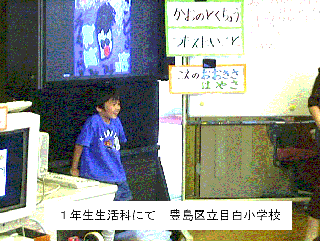(5)情報活用の基礎基本としての「情報の科学的な理解」
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と,情報を適切に扱ったり,自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解
( 調査研究協力者会議「第一次報告」1997より) |
情報活用の実践力を深めるために、情報に関わる知識(情報学)を学習する。
①情報の光の部分の学習
情報の科学的な理解は、「情報や情報手段の特性の理解」「人間の情報のとらえ方の理解」「情報手段のしくみの理解」と言える。今まで、人は情報をどのように利用して生活を便利にしたりしてきたか。情報科学はどのように発展してきたかなどを理解する。
協力者会議による情報学の内容
(従来のコンピュータや情報通信などの分野を中心とした情報科学に加え、人間科学や人文社会学等への学際的な広がりを持った学問)
・人間の問題解決に役立ってきた,シミュレーション手法やモデル化、情報処理など がどのように役に立ってきたのか,情報の信頼性や有効範囲などを評価するためには どんな能力が必要かというような基礎・基本の考え方
・人間の認知的特性を研究対象とする分野,人間の学習や思考,コミュニケーション の特性を解明し,人間の優れた特性の生かし方や弱点の克服の仕方を示唆する
・コンピュータ等の情報機器の普及や情報通信ネットワークの基本的仕組みを理解 し,適切な活用方法を知ること
( 調査研究協力者会議「第1次報告」1997をもとに筆者がまとめたもの) |
情報の科学的な理解についての学習は、以下の場面で行われる。
・教師側で情報学の内容に基づいて授業や学習活動を設計し,その時々に必要な情報の 扱い方や機器の操作を子供たちに体験的に習得させるようにする。
・人間の情報に関する体験を振り返ったり、実験や実習を取り入れながら,それらの存 在を明らかにして,その役割を理解させ、さらにそれを主体的に活用する実践活動と, その活動の評価・改善を経て,知恵として定着させる。
② 情報の科学的な理解の内容
高等学校段階までにすべての子どもたちに履修させたい「情報の科学的な理解」の範 囲としては,発達段階を考慮しながら,以下の内容を扱うことが考えられる。
・伝えたい情報を,伝えたい相手の状況などを踏まえて,より効果的に伝えるための 文字,音声,画像などのマルチメディアの表現法や,数式,図,表,アルゴリズム(手 順)などの事象間の関係を表すための情報の表現法。
・文字,数値,画像などのデータを効果的,効率的,かつ,高精度で処理・加工する ための情報処理の方法。
・実験・観察,調査などのデータを正しく収集し分析するための統計的見方・考え方 や,そのために必要となるモデル化の方法。
・将来の結果予想や,与える条件を変えることによってどのように結果が変化するか を知るために有効となるシミュレーション手法。
・情報を的確かつ効果的に伝えたり,誤った情報の判断を未然に防ぐ上で役立つ,人 間の感覚・知覚や記憶,思考などの認知的特性。
・家電製品などに広く使われている計測・制御技術やインターネットなどの身近な情 報技術の仕組み。
・情報の伝達や処理,記録などに活用される代表的な情報手段の機能の分類や,長所 短所,類似点・相違点,活用に適した場面と適さない場面など,情報手段を活用する 上で必要な情報手段の特性。
上記のほか,児童生徒の興味や関心に応じてさらに深めた学習や発展させた学習ができるようにすることも必要である。 ( 調査研究協力者会議「第一次報告」1997より)
|
③小学校段階からできる情報の科学的な理解
| 情報の特性というと、今までの学習活動で 考えることが少なかったが、古藤泰弘氏(1999) は「情報とものとの違い」を右のようにまと め、図で表している。「情報とは何か?」と いう問いをしたり、情報機器の特性というも のを考えたりすることは、小学校段階からも 必要である。これらは、パソコンや情報通信 ネットワークを使っていて、情報社会特有の 現象に出会った時の対処の仕方や、日常生活 の中の情報化を発見したり、疑問を持ったり するために必要な知識である。また、情報技 術の能力形成にも重要な役割をしている。 |
|
. .
ものと情報の違い
●実体 ●情報
∥ ∥
●実在 ●知らせ、報せ
↑ ↑ |
|
直接・実体験
五感 |
|
間接・疑似体験
ことば、映像
模型、疑似装置 |
|
| |
(古藤泰弘『インターネットで総合学習を立ち上げる』明治図書1999) |
|
右の写真は、実際の指導例である。小学 校1年生の生活科の授業「じこしょうかい をします」の中で、自分の顔を書いた絵の 前に実際の人物を出して比べて意見を言っ ている場面である。絵は情報である。小学 校1年生でも、このような経験を通して、 児童は本人(実体)と絵(情報)の違いに 気づくようになる。